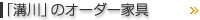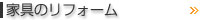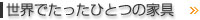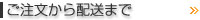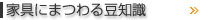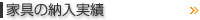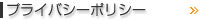株式会社溝川【オーダー家具の製造・販売】

材料
無垢板(むくいた)
正真正銘の一枚板のこと。長厚で高級感があるが歪みやすい。
ソリッドとも言う。
突板
美しい木目の部分をスライサーで突くようにして削った、厚さが1mmも満たないような薄い単板。
それを板に貼ったものを化粧板と呼ぶ。
集成材 <<クリックすると画像を表示します。
小幅の木材を同じ繊維方向に接着させながら一定の厚さに成形した板。
無垢板としての欠点を除去した均質で最大な材を作ることが出来る。
木質繊維板
木材をチップ状あるいは繊維状に分解し、接着剤で圧縮成形した板。
パーティクルボードやMDF(中密度繊維板)、ハードボード等の事。
寸法安定性や加工性に優れるが、水に弱く衝撃に弱い。
合板 <<クリックすると画像を表示します。
丸太を大根のかつやむきのように薄くスライスした短板を、繊維方向に交差させて接着したもの。
繊維方向によって物性が異なる木材の欠点を、短板を交差することで平均化し寸法安定性も高まる。
家具のフラッシュ構造には欠かせない材
F1合板
ホルムアルデヒド放散濃度が極めて低い合板。
JAS規格で0,5mg/L以下をF1、5mg/L以下をF2、10mg/L以下をF3と区分している。
バーチ合板
合板と同じだが、全ての層の短板がバーチ材で出来たもの。
繊維方向は交差するが、表面だけでなく内部も同質の材であるため切り口が美しく、その木口を活かして家具の部材に利用することもある。
LVL(単板積層材)
単板を交差させ接着したのが合板であるのに対し、単板の繊維方向を平行させることによって一方向の強度を高め、より自然の材木に物性を近づけたもの。
平行に単板を重ねることから平行合板と呼ぶこともある。
パーティクルボード <<クリックすると画像を表示します。
小さな木片に接着剤を添加しパネル状に成形し、圧力をかけて作る。
従って合板を作るときよりももっと小径木や端材などが利用できる。
断熱・遮音性にも優れ、均一で経済的な材料だが木口部からの吸湿に注意が必要。
MDF(中密度繊維板) <<クリックすると画像を表示します。
パーティクルボードの場合、木片が確認できるが、MDFの場合は木材繊維の段階まで細かく成形する。
従って表面が滑らかで堅く木口が緻密で加工性・研磨性に優れている。
エナメル塗装の基材としてや、MDFの表情をそのまま表現した家具も増えてきている。
唐木
紫檀、黒檀、鉄刀木(たがやさん)、花梨など、熱帯産の希少価値が高い高級銘木の代名詞。
いずれも色合いが濃くて硬質な材。
昔は中国を経由して輸入されていたのでこう呼ばれる。
杢(もく)
木目の紋様で、特に装飾価値が高い木理を「杢」と呼んでいる。
ブナ科の虎斑杢やメープル等に現れる鳥眼杢、トチ・シカモア等の縮み杢の他、縞杢、葡萄杢、牡丹杢、鶉目、如鱗杢などがある。
柾目・板目(まさめ・いため) <<クリックすると画像を表示します。
丸太の中心に向かって挽いた時に現れる年輪が平行な木目を柾目と言うのに対して、中心からずれて挽くと平行ではなく、山形や筍形の木目が現れ、これを板目と言う。
加工
指物
板や角材を組合せて箪笥や机、箱などの家具調度品を作ることの総称。
それを専門に作る職人を指物師と呼ぶ。
組手
二つの部材を組んでつなぐ時、木口(こぐち)に細工を施して接合部の強度を高める工法で、継手、仕口とも言う。
各種の伝統的な組手があり、接合箇所に応じて使い分けされる。
蟻組み
引出しの前板と側板を接合する時の代表的な組手。
ほぞの先端が広がっているので、引張り強度が大変優れている。
ほぞ <<クリックすると画像を表示します。
角材や板を接合させる時、部材の端を凸状に加工した突起を「ほぞ」と言い、それを差し込むための凹状のくぼみを「ほぞ穴」と言う。
ダボ <<クリックすると画像を表示します。
部材を接合させる時、双方に穴をあけておきその中に挿入する木製の丸棒の事。
ドイツから伝わった工法で生産効率が良く、「ダボ組」または「ダボ接ぎ」と言う。
また、棚の高さ調節するための棚受の事もダボと言う。
木釘
文字通り木の釘。「うつぎ」や「つげ」等を釘状に削り、煎って硬くして使う。
サビが出ず仕上がりが美しい。
高級な和家具や細工物によく用いられる。
留 <<クリックすると画像を表示します。
二つの材を主として直角に接合させる時45°づつに分けて接合させること。
仕事や乾燥度合いが悪いと、後になって接合部が離れて口を開ける場合があり、「留が切れる」と言う。
面
部材の角を削り取って出来る装飾用の形状を「面」または「面形」と言い、几帳面の由来となった形をはじめ各種の形状がある。
角を加工することを「面を取る」または「面を付ける」と言う。
うづくり仕上げ
かるかや根の和箒(わぼうき)の繊維を円筒状に束ねた「うづくり」で、木材の表面を何度もこすって木目に凹凸を付け、年輪を浮かび上がらせた仕上げ方法。
特に、桐材の代表的な仕上げ。
UV塗装
紫外線を照射させて塗膜を硬化させた特殊な塗装。
普通の塗装より硬いので傷が付きにくい。
框組み(かまちぐみ)
角材を方形に組んだ枠を框と言い、その枠内に板(鏡板と呼ぶ)をはめ込んだ構造を框組みと言う。
古い箪笥や手作り家具の即板にはこうしたものが多い。
フラッシュ構造 <<クリックすると画像を表示します。
角材や厚板で枠組みをして、その表と裏に合板などを張ったパネルをフラッシュボードと言い、こうした作りを「フラッシュ構造」または「太鼓張り」と呼ぶ。
なお、片側のみ合板を張ったもの物は「片面フラッシュ」を略し「方フラ」と呼んでいる。
本体
台輪
箪笥など箱物家具の最下部に位置する台座の部分で、本体と一体化したものと分離できるタイプとがある。
天板(「てんばん」または「てんいた」)
箪笥、棚などの一番上の板で、「支輪」とも言う。
テーブルなどで言う甲板も天板と呼ぶことがある。
蝶番
「ちょうつがい」とも言われ、開き戸などが開閉出来るように取り付ける金具の総称。
蝶が羽を広げた形に似たことが由来。
英語ではhinge(ヒンジ)。
衣装盆
和箪笥などに装備され、和服を折りたたんで整理収納するための浅い器。
引出しと違い、本体から容易に抜き出して持ち運べる便利さがある。
現在は主に桐製で、蓋付きの盆もある。
ノックダウン式家具
組立て式家具のこと。自分で組立てるタイプは低価格であるが強度が劣る。
大型の婚礼箪笥で、部屋に入れ易くするために分割できるものもある。
こちらは、強度に問題はなく引越しに便利。
水屋
本来は、水を扱う台所などを水屋と称していたが、そこに置いて食器などを入れる戸棚のことを水屋と呼ぶようになった。
今で言う食器棚(cupboard)のこと。
チェスト(chest)
chestは胸部を意味し、高さがせいぜい胸までの小型の整理箪笥や収納箱を指す。
ワードローブ(wardrobe)
洋服箪笥。または個人の持ち衣装全体を指す。
キュリオケース(curio case)
curioは貴重品を意味し、それを陳列するケース。
一般には高級な飾り棚をキュリオケースと呼ぶ
スツール(stool)
背もたれのない一人用の腰掛け。
シェルフ(shelf)
商品や品物を展示、陳列しておく棚。
店舗での需要が多いが、家庭でも最近よく使われる。